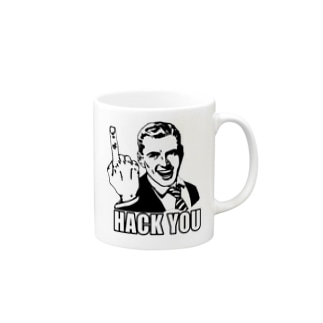長い間、ファンタジー映画が幅をきかせ、SFらしいSF映画が少ないと感じていたが、このところ見ごたえのある作品が封切られていたようだ。前回紹介した「オデッセイ」もそうだが、「インターステラー」もSF気分をたっぷり堪能できた。
私はSFと言うと、科学が物語の根幹を成しているような作品を指し、個人的には大好きなスターウォーズも、SFには入れていない。インターステラーは、ブラックホールや相対性理論など、本格的な物理の理論を扱っているので、なかなか難しい部分がある。とは言え、家族の愛やスペクタクルな大自然の猛威、人間同士の軋轢など、映画らしい楽しさが盛りだくさんで、多くの人が楽しめる作品だ。
また、往年の名SF映画「2001年宇宙の旅」へのリスペクトが散りばめてあったのも印象的だ。地球外からの呼びかけに気がつくきっかけが重力の異常で、他の宇宙への入り口が土星にできているというのは、「2001年」そのものだ。(土星は小説版の「2001年」、映画版は木星が舞台)。さらに、「2001年」で特に印象的な石版「モノリス」とコンピュータ「HAL」を合わせたような、板状のサポートロボットが登場する。これがなかなかのもので、登場した時はあまりにムリヤリな造形に少し興ざめしたほどだったが、ストーリーが進むに連れ、スムーズな変形と多機能ぶりに、むしろ合理的な設計のように思えてきたほどだ。
人類を救うため、ワープして未知の星系へ行き、居住可能な惑星を探す。そのために数年前に。一惑星に一人ずつ先乗りさせていた観測員を救助に行く。だが、思いもよらない出来事で次々と失敗してゆく。さすが宇宙は、主人公の思惑も映画的ご都合主義も、一切気にとめないのだなあと感心したほどだ。
とはいえ物語はなんとか解決する。多分、難解な物理の理論が見事に映像化されてるのだろうなとは思うのだが、肝心の理論を知らないので、味わいきれなかった部分はある。これは不徳のいたすところだ。
物事は決して思った通りにはならないが、悪あがきしてれば、思いもよらない幸運も訪れる。そんな私の人生訓そのもののような映画である。