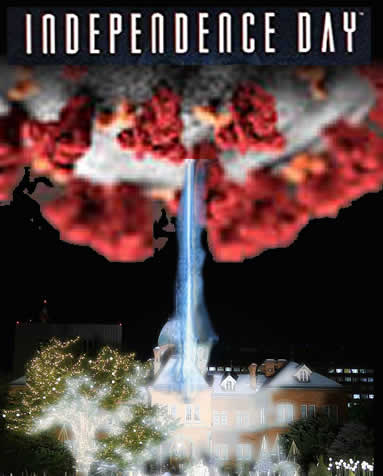2018年1月、中国人民解放軍の所有する商級原潜が、東シナ海の公海に浮上し中国国旗を掲げた。対潜能力世界一と言われる海上自衛隊に2日間追い立てられ、逃げ場を失って浮上し、いわば白旗を掲げた形である。このとき、映画「レッド・オクトーバーを追え!」を見たことのある人は、快哉を叫んだかも知れない。
「レッド・オクトーバーを追え!」は、トム・クランシーのデビュー作で、世界的ベストセラーになった同名小説の映画化である。この作品をまた見ようと思ったのは、ネット上の評価が大きく別れていたから。名作だという評価に対し、「長くてテンポが悪い」「難しい」などの意見もあり、私はこれは世代の差だろうと考えた。
小説が発表され、また物語の舞台となったのは、ゴルバチョフ政権発足直前の1984年。映画の封切りはソビエト連邦崩壊前年の1990年。20世紀の一大エポックともいえるソビエト共産党政権が内部から崩壊し、東西冷戦が終息しつつあった時代だ。当時の多くの人は、ソビエトの体質、冷戦の構造と原潜の脅威などについての知識を、多かれ少なかれ持っていた。それらを前提にしたこの作品が、冷戦終結後に生まれた人も多い現代でわかりにくいのも当然かも知れない。
長くてテンポが悪いという批判は、当たっていなかった。海中での潜水艦アクションだけでなく、陸上での行動や会話のすべてが、大都市への核攻撃や米ソの直接戦闘を引き起こしかねない。そんなスリリングなシーンだけでできている映画と言ってもいいほどなのだが、これも当時の時代感覚がないと、スリルのツボを味わいきれないかも知れない。
現実世界でも原潜の役割はレッド・オクトーバーの時代から何も変わらず、対潜水艦作戦は現在でも続けられている。そのことが垣間見えたのが、中国原潜の浮上である。原潜は何ヶ月も浮上せずに行動でき、一度見失うと発見は難しい。ある日突然東京湾に浮上して、核巡航ミサイルで日本を恐喝することも可能だ。原潜所有国は、横綱のいる相撲部屋のようなものだ。
一方水中では目視もレーダーも効かないため、いかに原潜でも、深海に沈められてしまえば発見はほぼ不可能だ。攻撃を受けたことを証明するものはなく、そんなものは知らないと言われれば、それ以上抗議もできない。そんな中で徐々に海淵部へ海淵部へと追い詰められていくのは、二日間拳銃を頭に突きつけられ、カチン、カチンと空撃ちされ続けるのと変わらない。発狂するものや、これを機に退役するものが出ても不思議ではないくらいだ。名誉や誇り、与えられていた命令をすべてかなぐり捨てて、国の財産である原潜と乗組員を守ることを選んだ、というのがあの浮上と国旗掲揚である。相撲に例えれば、日本は小兵力士ばかりだが、多彩な技の修練に余念のない横綱キラーばかり揃った、ヤらしい相撲部屋という感じだろうか。
「レッド・オクトーバーを追え!」は、世代によって評価の変わる、要するにジジイ世代の映画である。あらためて見終わって、つくづくジジイでよかったと思う。
ついでながら、今年5月公開予定の「GREYHOUND」の予告を。
「潜水艦映画に駄作なし」(ただし某日本映画を除く)とまで言われたジャンルの、期待の新作。第二次大戦中の、Uボートとの戦いらしい。”らしい”と書いたのは、ネタばれがいやで自分では予告も見ていないから。だが、原作は海洋冒険小説の金字塔「海の男ホーンブロワー・シリーズ」を書いた、セシル・スコット・フォレスター。主演はなんとコロナ感染前のトム・ハンクスである。劇場鑑賞は体がきついのでスター・ウオーズで打ち止めかと思っていたが、これはアリではないかと思う。5月ならコロナ終息を期待して、大画面で観たついでにちょっぴり経済を回すのも悪くない。